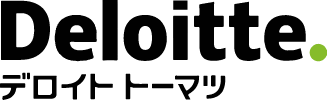平清水 元宣(ひらしみず・はるのぶ)
スタートアップ事業部 産学連携チームリーダー シニアコンサルタント
【プロフィール】
山形県出身。シンクタンクやコンサルティングファームを経て2021年6月入社。これまで大手民間企業の新規事業開発や戦略策定案件を複数担当。直近では大学発スタートアップの資金調達や大企業との産学連携支援をリード。
【経歴】
幼少期からサッカーを始め大学時代は部長を務めた。サッカーで学んだのはチームビルディング。個の力は重要と思いつつも、一人でできることは限られることを理解し、大きな夢の実現には思いを共有した仲間を後押ししながら進んでいくことであると持論を掲げる。現在も会社のフットサルチーム代表を担い、週末は専ら子育てに奮闘。実家である山形の寺院で18歳まで過ごした経験から「徳を積む」ことを重視し、イノベーション創出を通した地方創生や社会貢献に強く思いを持っている。
イノベーションに関心を抱いた理由は何ですか
「地方の共通課題を解決したいと考えたからです」
多くの「地方」は都心部に比べて移動手段が乏しく、魅力的な働き口も少ない共通の課題を抱えています。私は新規事業を創出することで、新しい移動手段を地域に普及させ魅力的な雇用を創出することで地方創生に貢献したいと考えています。
学生の頃は、移動課題の解決に向けリニアモーターカーの走行原理「超伝導」を学ぶために東京理科大学にて物性物理学を専攻しました。途中で壁にぶつかり研究者として成長するのは難しいと痛感し、シーズを世の中に送り届ける「技術の事業化」を担うコンサルタントを志す様になりました。
大学院修了後はシンクタンクやコンサルティングファームで働くご縁を頂き、研究開発や新規事業の戦略や企画をご一緒する経験をしました。しかし、戦略が絵に描いた餅で終わる歯がゆさを感じる場面にも遭遇したことで、より泥臭く技術の事業開発を経験できる環境を探し求め、DTVSに参画するに至りました。
DTVSでの印象的なプロジェクトは何でしょう
乗り合いタクシー事業を展開するスタートアップの地方進出支援です」
東京都のアクセラプラグラムで独自のAI技術によって乗り合いタクシー事業を展開するNearMe(ニアミー)社の地方進出等をご一緒するアクセラレーターを担いました。複数の自治体とのお引き合わせや導入を決めることにも貢献しました。後に私の地元である山形市への導入も決まり、ご一緒することができたことを本当に誇りに思っています。
その過程で得た気づきは、高度なテクノロジーやソリューションだからと言って、即導入になることはないということです。口先だけではなく、メール文章の一言一句にも気を配り熱い思いを込める努力をしたことを覚えています。ある自治体からは即座に断られることもありました。電話で1時間半くらい粘って思いを伝えたこともあります。
そのプロジェクトを経て自分自身、どのように変わりましたか
情熱を込めて目の前の業務と向き合うようになりました
結局、私に足りなかったのはパッションです。熱量が足りなければ人の感情を揺さぶることはなく、ましてや新規事業が顧客を感動させ熱狂的なファンを作ることもできません。コンサルタントは論理的なことが前提ですが、情熱が備わっていなければ何も成しえないと改めて痛感しました。いまではとにかく情熱を込めて目の前の業務と向き合っています。最近では「担当が平清水さんで本当に良かった」と言って頂ける機会が増え、「これが私の介在価値なのかな」と胸を張って言える様になりました。
今後の目標を教えてください
「大学発ベンチャーをユニコーンまで押し上げていくことです」
地域の産業クラスターを掛け合わせた大学発ベンチャーを創出し、ユニコーンまで押し上げていきたいです。各地域・産業の優位点を見極めた上で、企業・自治体に支えられて成長する会社を1社でも多く輩出したいを考えています。大学発ベンチャーは大学の高度な研究力や技術力を兼ね備えながらも機動力がある組織体の為、技術の事業化を牽引する組織です。
また、地域の大学発ベンチャーがユニコーン級の規模の会社へと成長することで地域に雇用が創出され、その企業を中心に子会社や関連会社が誕生することで雇用が更に生み出される好循環が構築されると考えています。結果、地方自治体の税収入も増え町の魅力度が増し、若者も定住し人口も拡大するようになる。大学発ベンチャーを生み出した大学の魅力も向上し、優秀な学生が入学する好循環も生まれます。そんな大学発イノベーションによる地域のエコシステム形成と発展に貢献していくことが、私の目標です。
具体的にはどのような形でプロジェクトに携わっていきますか
「大学院で学んだ知財戦略の活用です」
研究シーズの技術がどこで使われる可能性があるかを探索する用途開発と、参入障壁を形成する知財戦略の策定に注力しています。特に大学発ベンチャーは知財権の獲得によって資金を調達でき、その資金で人・モノ・情報をさらに充実させることが可能となります。
言うほど簡単な挑戦ではなく、日々、新しい技術を学び続けてはトライ&エラーを続けています。知財戦略を深く学びたいと思い母校の大学院で知財戦略を学び直したこともあります。挑戦は始まったばかりですが手応えは感じています。大学発イノベーションを通して地方経済の発展に貢献できるコンサルタントとして成長していきたいです。