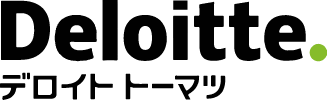浮島 望(うきしま・のぞみ)
ビジネスプロデュース事業部 Startup Compassユニット コンサルタント(2025年4月現在)
【プロフィール】
東京都出身。2022新卒入社。大学院では行動経済学を専攻とし、経済学修士号を取得した。DTVSの自社事業であるStartup Compassの開発に従事しており、新規事業の成功確度を高めるため体系的な知識を有する。
【経歴】
クラシック音楽の鑑賞が趣味で、自宅ではレコードで鑑賞し、休みの日にはコンサートに出かけることもしばしば。その一方バスケやゴルフ、ウェイトトレーニングなどのスポーツも日常的に楽しむ。経験に基づいた経営支援を行うために、将来的に起業も視野に入れている。
ご自身のご経歴と、スタートアップ支援に関わるようになったきっかけを教えてください。
学術機関の研究を社会課題の解決に活かしたいという想いがきっかけとなりました。
在学中は、経済学の研究をしており、特に社会課題の解決に経済学的アプローチを取り入れることに関心を持っていました。たとえば、アメリカでは腎臓移植の効率を最大化するために経済学者がマッチングアルゴリズムを設計し、実際に社会実装されるなど、研究が社会に直接影響を与える事例が多くあります。一方で、日本ではこのような経済学的視点をビジネスに活かす機会がまだ少ないと感じておりました。特にスタートアップの世界では、単発のプロジェクトではなく、中長期的に成長するビジネスをどう生み出すかが重要だと思っています。こういった課題を解決するために、私はスタートアップ支援の領域に関わるようになりました。
入社後はどのようなプロジェクトに関与されていましたか?
主にStartup Compassという社内新規事業を担当しています。
起業家のメンタリングや大企業のコンサルティングをさせていただく中でも、やっぱり自分でやったこともないのにアドバイスすること自体、何様なんだろうという後ろめたさが残っていました。なので、まず自分で何かをやってみたい、今できることは何かと考えたときに、社内新規事業に関与するという答えにたどり着きました。私が関与させていただいているStartup Compassという事業は、主に、大企業の新規事業担当者に向けたデジタルツールを提供しています。具体的には質問項目に沿って検討中のビジネスモデルを記入していくと、その事業フェーズにおいて検討が必要な項目や、PMFに向けて足りない要素を洗い出し、適切なフレームワークが出力されるというサービスです。最初に何を考えたらいいかわからない新規事業の担当者に対し、考え方を示して差し上げるようなイメージです。このプロジェクトの中で自分自身が社内事業担当者として一つのサービスを作り上げるという経験を積むとともに、新規事業の立ち上げや仮説検証に関する支援サービスの提供を通して体系的な知識を身に着けることができたのではないかと思っています。
自分自身にとって、ブレイクスルーとなったような経験はございますか?
セオリー通りの支援では通用しなかった、ASACでのアクセラレーターとしての経験です。
多くの経験が自分の成長の糧になってきたと思っていますが、やはり印象に残っているのはASACを通したシード期のスタートアップ支援ではないでしょうか。このプロジェクトには入社してから3年間ずっと携わらせていただいています。スタートアップはフェーズが進めば進むほどやることは明確に絞れてきて、支援に求められることも専門性が増してくる。その一方で、シード期のスタートアップはやらなければいけないことが非常に多岐にわたっていて、これをやれば成功するといったようなセオリーが通用しません。前提として、仮説検証や資金調達にかかわる知見をもって支援に当たらせていただいていますが、これまで支援に携わらせていただいた6社すべてで全く異なる対応が求められました。例えば、ASACの採択期間中にスタートアップのチームメンバーどうしがぶつかり合う場面にも一度ならず立ち会うことがありました。その際は、我々が第三者としての立場を生かして、対面の打ち合わせを設定するなどの調整させていただくこともあります。その結果、あるスタートアップのメンバーからは「久しぶりに腹を割って本音で語り合うことができた」といった言葉をいただくなど、再度前向きに事業を進めるきっかけをつくれたのではないかと考えております。こういった験を通して、セオリー通りのアドバイスだけを行うコンサルタントというよりも、あらゆる手段を講じて事業を前に進めるため、一緒に伴走をする支援家としてのマインドが醸成されたのではないかと感じています。創業期のスタートアップの支援には事業計画書がどうとか、業界的にどうとかではなくて、今目の前のこの会社に本当に必要なことは何かなど、本質的な部分を常に考える視点が重要だと腑に落ちた経験でした。
起業家の支援に向けてどういったスタンスを重要視されていますか。
本質的な目的を見失わずに、事業を持続するための「問いかけ」を重視しています。
多くのスタートアップは、壮大なビジョンを掲げて資金を集めるものの、短期間で事業が停滞してしまうケースが少なくありません。一方、大企業でも、新規事業開発することが目的となってしまい、実際の市場ニーズに根ざしたビジネスにならないこともあります。そこで、私は起業家に対して「本当にこの事業モデルは持続可能なのか」と問い直すことがあります。例えば、ビジョンを実現するため、まずどういった顧客にアプローチすれば、将来的に事業を拡げていけるのか、そのための成長モデルとして何が適しているのか。単なる資金調達ではなく、将来の成長を見据えた資金計画の策定ができているのかー。このような問いを通して、起業家が一時的な成長ではなく、長く続くビジネスを築けるような支援を心がけていきたいなと思っています。